こんにちは。全国で講演、セミナー研修など行っている
農業講演家の山下弘幸(やましたひろゆき)です。
農業歴35年。親元就農後、個人、法人の農業経営を経て
農業コンサルタントに転身し、
現在、新規農業者、若手農業者、企業農業参入支援などをしています。
具体的には、稼げる農業を実現する
”1歩先行く農業者”のオンラインコミュニティ
「農業ビジネススクール(農ビジ会)」を主催し
全国200名の農業者と毎月勉強会や情報交流を行っています。
また、定期的に更新しているyoutube(農テラスチャンネル)では
全国の農業者へ「農業経営・農業ビジネス」の最新情報をお届けしています。
さて、今回の山下弘幸農ビジコラムテーマは
「稼げる地域」の作り方
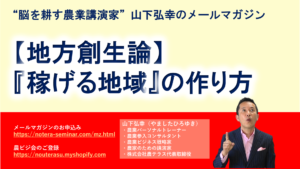
最近、稼げる農業をやるにはどうすればいいですか?というご質問より、
農村地域を活性化させるにするにはどうすればいいですか?
というご相談が増えてきました。
確かに、地方を救うには“稼げる農業”だけじゃ足りません。
私は行政や街づくりの専門家ではありませんが、
政治家になったつもりで私なりの地方創生論をまとめてみました(笑)
前提として
地方を活性化するためには、理想論ではなく現実的な「財政戦略」が必要だと考えています。
そこで「鍵」となるのは「財政の確保」。
なぜなら多くの地方財政がひっ迫しているからです。
その方法は大きく分けて「歳出の見直し」と「歳入の確保」の二軸です。
【財政の見直し】
歳出の見直しにおいては、行政の非効率な支出、いわば“コストの垂れ流し”をなくすことが第一歩。民間委託できる業務は積極的に外部化し、自治体は戦略的な役割に集中すべきだと思います。
ただし、イーロンマスク氏のように効率化ばかりを求めるのもいかがなものか・・・。
一方、歳入の確保は3つの柱があります。
「プライオリティ政策」
「広域連携プラン」
「インディペンデント構想」
第一に「プライオリティ政策」。これはこれまで平等に配分していた予算を見直し、教育や医療、子育てなど優先順位の高い領域に再投資する戦略です。
このかじ取りはとても難しい課題ですが、避けて通れない最重要課題だと思います。
次に「広域連携プラン」。自市だけで抱え込むのではなく、他の市町村と連携し、広域での予算獲得やプロジェクト推進を目指します。特に重要なのは災害有事受け入れ提携です。
もしもの時に食と住まいを提供する市町村間で連携できる仕組みを作ります。
これには財政に余裕のある地域から財源支援、協力も含みます。
さらには企業版ふるさと納税を連携地域の企業に促します。これからの時代は官民融合を促進する地域が生き残れる時代だと考えています。
そして第三は「企業誘致」による固定資産税の確保と、「子育て世代の流入」による所得税の確保です。
企業誘致は災害に強い街をアピールする必要があります。リスク対策も重要ですが、これには限界があります。それよりBCP対策(有事災害が起きた後の対策)を強化します。
【住民のエンゲージメント】
また、子育て世代の流入促進にはまず、既存住民の流出を防ぐことが重要です。
この二つを同時に行うために「住民エンゲージメント」の向上とシビックプライド(地域や都市に対する市民の誇りや愛着、地域社会への貢献意識)の定着を進めます。
なぜなら
そこに住む住民が自分の町を悪くいっているようでは新しい人はやって来ないからです。
具体的な政策として住民参加型の町づくりとして、バルセロナやヘルシンキなどで使われている、「デシディム」のようなオンラインプラットフォームを使った意見集約も導入します。
デシディムとはオンラインで多様な市民の意見を集め、議論を集約し、政策に結びつけていくための機能を有している参加型民主主義プロジェクトのためのオンラインツールでのことです。
これにより市民の声を直接政策に反映させることが可能になり「自分たちの町は自分たちが作るんだ」という当事者意識を高めることが期待できます。
【子育て世代が選ぶ町へ】
さらに、教育・保育・医療・食育など子育て支援政策を充実させ、女性を中心とした子育て世代が“選ばれる町”をつくります。
これからの時代「子供のいる地域」が地方をリードします。ただし、この施策は受け入れる地域側住民の意識改革がとても重要になります。
そして次の構想が「インディペンデント構想」。
街の根幹であるエネルギー・食料・水の自立化を図り、災害や外部依存に強いスマートシティを目指します。理想論になりますが各家庭へ自家発電(再生可能エネルギー)と蓄電池(電気自動車など)の普及を促し有事や災害に備えます。
また農家と住民の紐づけも需要な政策になります。農家と消費者がつながることで食不足の不安を解消します。
農村問題として重要視されている耕作放棄地も民間に権利をゆだねる「耕作放棄オーナー制」を導入し社会全体で解決できるように整備します。
これから地方の人口減少は止められません。そこで対策としては「関係人口」の増加に力を注ぎます。観光やイベント、お試し移住、二拠点生活などを通じて地域と関わる人を増やし、その中から定住者が生まれる流れをつくります。そのためには「〇〇王国宣言」といった地域ブランディング、キャラクターなどで街を色付けしていきます。この明確なイメージ戦略(ブランド戦略)が未来の街づくりには効果的だと考えています。
また、根本的な“魅力ある町”づくりとして、「ウェルビーイング都市」の発想が重要です。
たとえば「よく眠れる町」「人が優しい町」など、心地よい生活を実感できるメッセージを打ち出し、住民の満足度、幸福度を高めていきます。
このように経済的にも精神的にも持続可能な地域を目指す3つの柱。
「広域連携プラン」「インディペンデント構想」「プライオリティ政策」
最後に、お金の使い方として、「オーナー&ファウンダー支援制度」を設けます。
地場企業が新たに創業するプロジェクトを支援できるようにします。
地元企業が地域を支える新事業やサービスを立ち上げる際に助成する仕組みです。
これにより仕事と雇用を創出します。
これからは「稼げる地方」の時代の幕開けです。
未来を選ぶのは、今ここに生きる私たちではないでしょうか。
最後まで私の妄想にお付き合いいただき、ありがとうございました。

