農業,農村課題を経験と知恵でサポートする
農業戦略家の山下弘幸です。
さて、今回のテーマは
技術は「良い」だけじゃ動かない 農家が意思決定する3条件
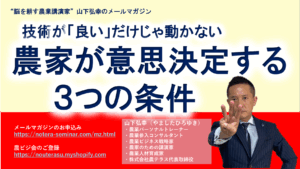
農業者に新しい技術を普及させたい。これは農業普及員や営農指導者のみならず、
農業関連の資材、機械、サービスを提供する企業が抱えているテーマです。
今回は農業発展のために農家に技術サービスを普及させる方法について
農家の私が解説させていただきます。
「いい技術なのに、なぜか農家に刺さらない?」
その理由は“農家の本音”と“導入判断の物差し”を読み違えているからです。
つまり、技術は“良い”だけでは農家は動きません。
農家が求めているのは「一発の最高値」ではなく、不作年でも崩れない最低値の底上げです。
本質は、①光・水・CO₂の管理で光合成を最大化できるか。そして導入の可否は、②材料費8–12%ルールの中で再現性ある数字に落とせるかで決まります。
例えば新技術30万円/年の投資なら、必要売上増は ΔS=30万÷0.12=250万。
つまり③年商1,000万の農家へ新技術を提案するなら、「売上を1,250万まで伸ばせると約束できるか」が勝負です。
このように農家が新しい技術を入手する心理には3通りあります
・収量を増やすことがステータスの農家
・売上を増やすことがステータスの農家
・利益を増やすことがステータスの農家
この安定と増やすという2つのキーワードを理解していないと農家の心には届かないのです。
1, 再現性の約束
まず、収量を増やすための技術について。
ここと、見落としがちなのが収量を減らさない技術との混同です。
例えば薬剤散布は収量を増やすのではなく、収量を減らさないための技術です。
一方植物活性剤などの葉面散布は収量を増やすための技術です。
また、除草作業は収量が減る病害虫の要因につながる恐れがあるので収量を落とさないためのリスクヘッジであると考えられます。
私は野菜農家ですので、野菜の場合で言えば
収量を増やすロジックは野菜が健全に育つこと。つまり健全に育つ野菜の環境を
整えることにつながる技術が農家に求められているのです。
では野菜が健全に育つために何が必要なのでしょうか?
それは光合成の最大化です。
植物の生きる目的は子孫の繁栄。そのために日々光合成という活動を行っています
つまり、農家に刺さる技術の提供のポイント①は本質的な光合成の最大化につながる技術だから再現性がありますよと訴求できることです。
2, 農家の物差しとスマート農業
次に売上を増やす農家の課題は取り扱い量と規模拡大です。
売上は農家の総出荷量と単価で決まります。単価は農家にはコントロールできないので、農家は総出荷量を増やす努力をします。
そこで、最初に取り組むことが生産規模の拡大です。シンプルに作付け面積が広がれば総出荷量は増えるからです。
ところが、農業はそう単純なものではありません。10を20に拡大したから
穫れる量も2倍なる。とはいかないのです。
理由は2つ手が行き届かなくなることと、目が行き届かなくなることです。
手が行き届かない。これが人手不足ということです。目が行き届かない。これは
管理不足ということ。つまり時間や労務、お金などのマネジメントが不足するということです。
そこで救世主として登場する技術が自動操舵、自動機器、遠隔操作、無人稼働、、センシング技術によるデータ集約などのスマート農業機器たちです。
これらは私が就農した35年前の農家が楽するための省力化が目的ではなく
出荷量が大量に取り扱えるための生産拡大技術なのです。
つまり、農家に刺さる技術の提供のポイント②は農家の物差しは規模拡大と収量増が比例するか否か。
最近農業用ドローンが普及してきた理由は、広い面積の田畑を短時間で防除できるからです。
3, 導入現場の痛点に寄り添う
ただ、これら技術を導入するには大きな投資が必要です。
農家は潜在的に投資するか否か判断する際に「利益」が残るか否かを計算します。
中にはどんぶり勘定の農家もいますが、得てしてそういう農家が導入した技術は
普及しません。なぜならその農家はつぶれていくからです。
つまり、これまで財務管理が苦手な農家に普及させた技術や売りつけた機器は農家がつぶれることで「ダメな技術」としてレッテルを張られてきたのです。
では、本当に農家に役立つ技術を普及させるにはどうすればいいのか。
それは費用対効果を得る規模の農家に届けるということです。
例えば新しい農業資材を導入するために毎年30万円のコストがかかる場合
農家の経費構図から逆算すれば
農業資材などの材料費は経費全体の8%から12%です。つまり売上1,000万の農家の材料費は80万~120万。農業所得が300万(30%)だと仮定します。
そこにはタネ代、肥料代、農薬代等が含まれますので、新たに30万の農業資材(技術)を導入すれば材料費が110万~130万とふくらみます。
しかし、仮にその技術を導入したところで売り上げが1,200万~1,250万まで伸びればこれまで同様に材料費は10%前後に収まります。
もちろん、農業所得も30%を維持できれば360万まで伸びる可能性が出てきます。
つまり、農家に刺さる技術の提供のポイント③売上収益を試算したうえでその新しい技術を導入すべきかどうかを提案してもらうことです。
農家はこの現場のリアルな痛点に寄り添って欲しいと思っているのです。
4, 技術の押し売りが農家を衰退させた
農業って、世の中にめちゃくちゃ多くの人が応援してくれています。
農林水産省、都道府県の農政部、市町村の農政課、全国の農協、農業関連企業
農業高校、農業大学・・・
あるデータによると農業関連、農業関係機関で働いている人は約30万人だとか。
食品関連を入れれば100万人を超えるそうです。
一方、平成7年時点での基幹的農業従事者は約110万人。
一人の農家に対して支援してくれる人々の多さに驚きます。
しかし皮肉なことに、農家の数は減る一方です。
農家のためにと技術は革新し続けてきましたが、もしかしたら
その技術の導入は逆に農家衰退のトリガーになっていたのかもしれません。
話しをまとめると、
そもそも農家は新しい技術を欲しがります。
しかし技術を入手する心理には3通りあることを忘れてはいけません。
農家、農業現場を本質的に伸ばす技術は良いのですが、農家を“客”にするための
技術やサービスも氾濫しています。
しかし、それを見極めきれない農家が多くいます。これも農家が減る要因の一つだと
思っています。
6、「農家の不安」を減らしたい。
とはいえ、これらの農家を支援しなければいけない立場の人たちは大変です。
なぜなら、農業を持続継続そして発展させるために新しい技術を普及させることは
不可欠だからです。
しかしそれが農業を衰退させることにつながっているの可能性がある?
とは考えたくないはずです。
誤解していただきたくないのですが、
決して普及側、指導側に問題を押し付けているのではありません。
あくまで
農家が意思決定する心理を知っておいてください。というお話です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【お知らせ①】
10月の農ビジセミナーお知らせ
第62回 令和7年10月10日(金)19:00~
今回も農ビジ会のメンバーにご登壇いただきます
地域農業コンサルタント
株式会社 アグリード 代表取締役 栗田 直樹 氏にご登壇いただきます
以前西の軽井沢と呼ばれていた避暑地。今では人口が600人にまで減り続けている
広島県のとある町を復活させるプロジェクトについて熱く語っていただきます。
地域創生のカギとなるのは農業・食・そして人。
全国の地方が抱える過疎化問題。みんなで考えてみたいと思います。
たくさんのご参加お待ちしております(^^♪

